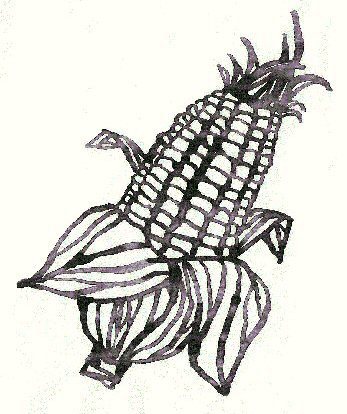|
サン・マルコス司教館として司教区全域で被災者への支援に当たるよう、緊急支援にむけての会計を一つにまとめて、そこから各地への支援経費などを出している。司教館を構成する16の組織には、社会司僕委員会、女性司僕委員会、カリタス、MTCなどがあり、各組織が援助のテーマや対象地域を定めている。
他にサン・マルコス県内で活動する組織では、土地問題をテーマとして草の根のメンバーを持つMadre Tierra、先住民族テーマを中心とするAjchimolやFundacion Mam、様々な労働者組合他あり、相互調整ができる組織とできない組織がある。
CONRED(Coordinadora Nacional para la Reduccion de
Desastres de Origen Natural o Provocado 災害対策調整会?)法により、地域の政府機関及び自治体や地域組織などの参加による緊急対策調整会(COE-Coordinacion Operativa de Emergencia)を県・市・コミュニティのレベルで設置することが定められている。実際には今回の災害に対応する中で体制を作り始めており、十分な調整能力を有していない。
どこの地域でも、援助が政治的に利用されている様々なケースが見られている。救援物資を受け取った市長が、自分を支援する周辺住民にこれを配ってしまい、被災者には届かない、という話はどこでも聞かれる。サン・マルコス県で住民の反対を押し切って鉱山開発を進めるモンタナ社は、インフラ改修や救援物資配布に乗りだして企業イメージの塗り替えに務め、政府はこれを賞賛する。
一方で、援助をこれ以上待つこともできない最も困難な状況にある被災者は、既に低地やメキシコの農園に出稼ぎに出始めている。これまででも法定最低賃金の半分しか払わない農園が多く、さらに安い賃金で利用されることが心配される。
MTCの方針としては、政府が被災者への援助を行う責任を遂行するようプレッシャーをかけると同時に、関係機関・自治体・外部援助組織による援助の展開に地域組織が参加していくよう、地域組織強化を重視しながらその調整を支援し、また社会監査システムを強化していく。MTCとしては県レベルのCOEに参加している。
MTCの緊急援助計画(10−12月)では、各地域の詳細な被災状況の把握、住居建設資材援助、組織強化を中心としている。住居を失い、同じ場所に戻ることが危険である被災者に、市他が土地を提供するよう交渉すると同時に、最低限の建設資材を早急に提供する。まだまだ必要性の高い食糧及び医療援助に関しては、国家機関や司教館から取り付ける。こうした地域組織の活動を支援するために低地と高地に1名ずつファシリテーターを付ける。また復興資材として、今回の洪水で流されてきた巨大な岩石を崩して砕石を作ったり、ブロックを作る機材を提供し、被災者が仕事と収入を得られるようにすることも考えている。支援の対象は、MTCの活動地域10市(低地6市、高地4市)の被災者全員とし、参加メンバーであるかどうかは問わず、地域住民同士の連帯を強化する。MTCとして活動してきていない地域でも、教会や地域組織を通じて支援するケースもある。
復興の段階では、ハリケーン前の状態に戻すのでなく、地域開発に向けて前進させる、尊厳のある生活を達成するために、地域住民組織強化は必須。
社会司僕委員会の計画では、12月までの緊急フェーズにおける食糧援助(1万家族)、医療援助(5千人)、水道改修工事(30件)を予定。その後の復興段階では、以下のテーマを中心とする。
1.環境: 以前の状況とハリケーンの影響を受けた現状の分析から、将来への危険性を把握。
2.農民の経済的再活性: 補助金、クレジット。
3.被災者の再定住地確保: 休閑地を接収して提供すべき。(憲法40条)
4.住居: 尊厳ある住居を政府に要求する。(1軒あたりQ25,000の建設費用?)
5.市民参加: 村・市レベルの開発審議会他を通して地域開発に参加。
被災状況のとりまとめはまだ終わっていない。県のCONREDの事務所では、41ページに及ぶ、それぞれのコミュニティの被災状況までを集約したデータを作成しているが、だいぶ漏れがある。どの機関・組織もまだ情報収集を行っている段階で、その情報が共有されていない。
適切な支援や復興を行うためには、地域ごと、家族ごとの詳細な被害のデータが必要となるが、市や政府機関はそこまで行わずに大まかな数字だけで予算書を作成しており、MTCでは各地のプロモーターを動員して情報を集めている。
|